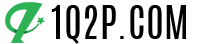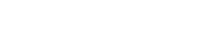マーク・レイドローは「400 Boys」を1981年、21歳の時に執筆した。これは彼がValveの主任筆頭作家となり、『Half-Life』の共同制作者となるはるか前のことである。当初はオムニ誌(1983年)に掲載されたこのサイバーパンク短編は、ブルース・スターリングのアンソロジー『Mirrorshades』に収録され、より広く認知されるようになった。自身のウェブサイトで、レイドローはこの無名の作品が皮肉にも、おそらく彼のDota 2のプロモーション文を除けば、他のどの作品よりも多くの読者に届いたと記している。ゲーム史が彼を『Half-Life』で記憶する一方、彼の創造的遺産はそれをはるかに超えている。
敵対するギャングが厳格な武士道規範に従う荒廃した大都市で、無政府主義的な400 Boysはかろうじて保たれていた均衡を乱す。エミー賞受賞監督で『ラブ、デス&ロボット』の「Ice」を手がけたロバート・バレーが映像化したこのエピソードは、詩的な暴力と衝撃的なアニメーションを見事に対比させている。
「その着想はオレゴンの街灯から生まれたんだ」とレイドローは振り返る。「電柱にはバンドのポスターが貼られ、刺激的な名前が並んでいた。あのエネルギーを作品に取り込みたかった。ギャングのアイデンティティを作り上げることが、物語の背骨となった。架空のバンド名を並べることが、やがて一つの物語全体を形作ることになろうとは、当時は知る由もなかったね」。

40年後、Netflixの『ラブ、デス&ロボット』が「400 Boys」に新たな命を吹き込んだ。声優陣のトップはジョン・ボイエガ(スター・ウォーズ)である。バレー監督(『Zima Blue』の監督)とブルー・スタジオのティム・ミラーが脚本を手がけたこの映像化は、原作者をも驚かせた。「サイバーパンクというジャンルが進化する一方で、私の物語はほこりをかぶっていた」と、シーズン4初放送前に行われたZoomインタビューの中でレイドローは認める。
この道筋は、15年も前にミラーが最初に権利を獲得した時に始まりかけたが、スタジオの再編により制作は棚上げにされた。そして2019年、『ラブ、デス&ロボット』が大人向けアニメに革命をもたらした。「ティムは、J・G・バラードの『巨人の溺死』がアニメーションの金脈になり得ると理解していた」とレイドローは述べる。「そのビジョンが私の信頼を得たんだ」。

パンデミック後のロサンゼルスでの打ち合わせが議論に再び火をつけた。2023年までに、バレーのチームはその本質を保ちつつ、散文を動的なアニメーションへと変えた。レイドローはパンデミック時代に制作したオーディオブックからの語り部分を提供したが、基本的には受動的に鑑賞するのを楽しんだ。「ボイエガの演技と視覚的ストーリーテリングが、私が十代に抱いた野望を、見分けがつかないほど高めてくれた」と、彼は驚嘆の念を込めて語る。
この作家は、今回の復活が一見つながらない点を結びつけたと認める。すなわち、ジャンル名が定着する前の彼のサイバーパンク的ルーツ、Valveの台頭、そして現在のNetflixによる映像化である。「文化的な転換点の一部となるには、とてつもない幸運が伴う」とレイドローは回想する。2016年にValveを去った後、音楽がゲーム開発に代わる創造の手段となったーー特に、紛失していた『Half-Life 2』の映像を共有したことでYouTubeのフォロワーが増えた後はそうなった。
ゲーム業界への復帰について尋ねられると、レイドローは冗談めかして、小島秀夫が『デス・ストランディング』の台詞の磨き上げのために自分を呼ばなかったのは残念だと述べる。もっと真面目に言えば、Valve退社後のオファーは、意味のあるプロジェクトというよりも、むしろモバイルゲームのあらすじに向いていたという。「『Half-Life』は、ゲームの脚本においては『少ない方がより豊かである』ということを証明した」と彼は語る。「それなのに、どういうわけか私は、人々がそのRPGをテキストで埋め尽くすことを望む『世界観を深堀りする担当者』になってしまった」。
『Half-Life 3』の問題については、決定的な終止符を打つ。「あの章は終わった」とレイドローは言い切る。「新たな創造者たちが、古参の干渉なしに、その未来を自らのものとすべきだ」。彼の関心は今や別のところにあるーーおそらく、数十年後にNetflixから必ずやってくるであろうHalf-Lifeの映像化企画を持ちかけられるのを待っているのかもしれない。それまでは、「400 Boys」が、芸術がいかに予期せぬ時にその時を見出すことができるかを証明する記念碑となるだろう。